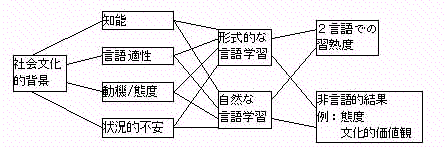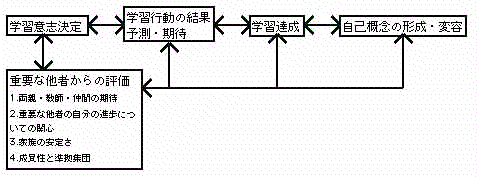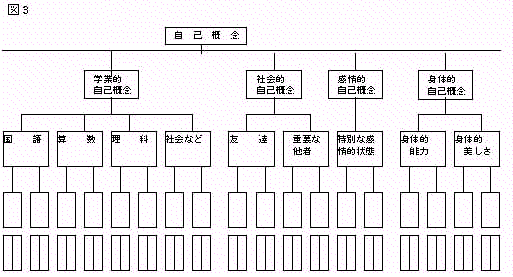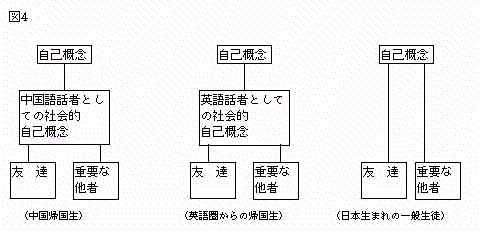バイリンガル能力の発達における社会文化的影響の研究
中国引揚者の子弟の言語環境を事例として
東京都立大学附属高等学校 清田洋一
研究の背景
現在、日本の学校現場では日本語を母語としない児童の数が増加している。海外勤務者の子弟、外国人労働者の家族、中国残留孤児、及び残留婦人の子弟など、これらの児童の大半は日本語以外の言語を母語とすると同時に、母文化として日本文化以外のものを身につけている。このような児童に対して、第二言語としての日本語を教えるためにはどのような配慮をしたらよいのか。彼らの母語と日本語との関係は一体どのようなものなのか。日本人が日本の学校内で英語の学習をするような関係とは大きく異なることは予想されるが、実際の学校現場では彼らの社会文化的な適応と関連して様々な問題が起きている(外国人子女の日本語指導に関する調査研究に関わる日本語教育担当者研究会、1997)。
特にこれらの児童の場合、彼らを取り巻く社会文化的環境の大きな変化が彼らの言語発達、つまり母語の維持と第二言語習得に影響を及ぼすことが予想される。しかし、その社会文化的要因のうち、一体何が彼らの言語発達を促進したり、妨げたりするのかについてはまだ明らかになってはいない。
早くから移民とその子弟の言語問題に直面しているアメリカやヨーロッパなどの国では第二言語習得やバイリンガリズム研究の中で、社会的コンテクストと言語習得の関係を研究してきた。一方、日本においては日本語というほぼモノリンガルに近い言語環境の中でこのような問題はあまり考慮する必要がなかった。しかし、近年、世界はこれまでの国境という枠組みが揺らぎ、ボーダレスの社会へと大きく変容しつつある。そして日本もその例外ではなく、多くの外国人労働者などのいわゆる異文化、異言語を受け入れつつある。平成7年度末現在における日本国内の外国人登録者は136万2,371人で過去最高記録を更新している(総務庁行政監察局,
1997)。また、平成7年度末現在における小、中、高等学校に在籍する外国人児童生徒及び、外国人学校に在籍する児童生徒の総数は約12万人である(総務庁行政監察局,
1997)。そして、海外勤務者の帰国子女や中国残留孤児の子弟などはこの数字には含まれてはいない。
日本においても帰国子女の適応の問題に対して心理学、文化人類学、比較教育、または日本語教育といった分野から様々な研究の取り組みがなされてきた。また近年、帰国子女だけでなく、外国人労働者や中国残留孤児といった新たな、異文化適応においてより深刻なグループへの調査、研究が行われている。そして、その子弟の言語環境の問題は日本の学校において重要な問題となっている。
またバイリンガル研究の立場から、帰国子女の言語発達についての調査研究も行われてきた。これは特に第二言語の習得モデルの研究に代表されるものが多い。これまでは、帰国子女や外国人労働者の子弟などの事例を言語習得や心理学的な立場などそれぞれの分野で個別に扱ったものが多かった。しかし、バイリンガル環境にある児童の例を見るとその言語発達と学校などの社会適応には不可分の要素があり、より総合的に彼らのバイリンガル能力を研究する必要がある。異文化、異言語を身につけた児童の第一言語と第二言語の発達とその社会文化的適応の関係を明らかにするためには、これまでのように個別の研究分野に留まっていた先行研究の成果を有機的に結びつける必要がある。
日本の教育現場における異文化適応の問題が海外勤務者の帰国子女のレベルに留まっていた段階では、「やがて日本人になる過渡期」の問題、または帰国子女個人のレベルの問題として扱われる傾向があった。しかし、南米系の海外労働者や中国帰国者の子弟の問題はこのレベルを超え、新たな日本人のグループの出現の可能性を示唆している。それは日本語を話さない、あるいは日本語を第二言語とするそれぞれの言語を核としたグループである。つまり、ポルトガル系日本人や中国系日本人といったグループの可能性である。その意味で日本におけるバイリンガル研究はヨーロッパやアメリカなどの移民の言語問題のレベルに近づきつつあると言える。
その観点から考えれば、日本におけるバイリンガル研究は個人の言語発達の問題から言語集団の問題としてとらえなくてはならない時期に来ている。ほぼ単一言語社会として、海外からの移住者に「同化」を強いてきた言語環境は、新たな言語集団の問題を抱え始めている。特に学校という教育現場では日常の教育活動の場で数多くの日本語を母語としない生徒を抱えてその問題に直面している。しかもそれはただ「日本語教育」だけの問題に留まらず、彼らの社会文化的アイデンティティーの確立といった問題と切り離すことのできない問題なのである。バイリンガル研究における言語グループの問題は移民の問題を抱える国々ではすでに様々な形で研究されてきた問題であるが、日本においてはまだほとんど研究の成果はない。しかし以上のような状況の下に、彼らの言語環境をめぐる研究の必要性は高い。
そして上記の問題が最も先鋭的にあらわれているのが、本研究で取り上げる中国残留孤児、及び残留婦人の子弟である。ここでは彼らがなぜ言語とアイデンティティーの問題を考える上で重要な存在なのかを述べておきたい。
子弟自身のことを考える前に、まずその歴史的背景として彼らの親、あるいは祖父母にあたる中国残留孤児と残留婦人たちについてふれる必要がある。その理由は子弟の言語やアイデンティティーの問題が残留孤児の歴史に深く関わっているからである。
残留孤児の発生には次のような歴史的な事情がある。太平洋戦争において日本が敗戦を間近にしていた1945年の8月9日にソ連が参戦し、それにともなって満州にソ連軍の侵攻が始まった。それまで満州に開拓団として移住していたそれぞれの開拓村の日本人たちは一斉に逃避を開始するが、開拓団の男子はすでに召集され、開拓村に「残されていたのは女と子供、それに病人と年寄りばかりになっていた(小川、1995)」。そのような状況下での逃避行は困難を究め、多くの子供たちが中国大陸に取り残される。これがいわゆる中国残留孤児である。彼らの帰国と肉親探しが始まるまでには様々な経過があるが、中国において彼らは文化大革命における排斥という経験を経て、自らが日本人であることを強く意識するようになる。
特にこの文革期には残留孤児自身だけでなく、その子供も学校などで他の中国人からのいじめを受けるようになる。現在、中国からの引揚者の学齢時の子弟は3世の代になっているが、本研究の質問紙調査において次のように記述する高校生もいる。
「中国では日本人といじめられた。日本では中国人といじめられる。一体自分は何人なのか。」
中国残留孤児や残留婦人自身は日本に帰国することに対してその出自から強い意欲を持つが、その子弟たちは必ずしも進んで帰国するわけではない。日本の教育現場において彼らは中国帰国生と呼ばれるが、そのほとんどが初めて日本社会に触れる。中国社会でその文化を母文化として身につけているものが急激な日本人化を経験するとき、その社会文化的適応において困難を経験することが予想される。これらの子弟を受け入れている学校では彼らの適応のために様々な取り組みを行っているが、彼らのアイデンティティー形成を考慮した望ましい言語環境の研究はまだ十分とは言えない。
研究の目的
近年、日本の教育現場においてその言語環境の問題が深刻化している集団として、南米からの海外労働者の子弟と通称「中国帰国生」と呼ばれる中国残留孤児、及び残留婦人の子弟の2つがあげられる。この2種類のグループは来日以前にはほとんど日本社会との接触や日本語教育の機会がほとんどない点で、いわゆる海外勤務者の帰国子女たちとは大きく異なる。
特に中国残留孤児の子弟は親、あるいは祖父母が中国引揚者という背景から、来日後、それまでの中国名を捨て、日本名を名乗るなどの急速な日本人化を経験する。しかし孤児自身とは違い、彼らは必ずしも進んで来日するわけではない。さらに青少年期という人格形成期にこの社会文化的な環境の急激な変化にさらされた場合、彼らのアイデンティティーの確立に大きな影響を持つことが予想される。そして彼らの日本における社会文化的な適応と人格形成にとって、中国語と日本語の二言語の発達は大きな意味を持つ。
彼らの社会文化適応とその言語発達に関して、これまでの調査で明らかになったことは以下の通りである(清田,
1995)。
- 彼らの中国語と日本語に対する態度の違いが見られた。言語学習の動機として、中国語は統合的動機、日本語は道具的動機の傾向が見られた。また中国語に対する高い象徴性が見られた。
- 中国語から日本語へと急速な言語移行が見られるが、情緒面での中国語に
対する依存度が高い。
- 親の世代に比べ言語を中心に同化傾向が強いが、その反面日本人グループへの反感も多く見られる。また、日本人グループに対して否定的な態度を持つものと日本語習得との相関では高いマイナスの相関が見られた。
以上のような点から、彼らが言語グループとして共通する特性を持ち、一般の日本人集団のとの接触において集団としての反応を持つグループダイナミズムの影響下にあることがわかった。
上記のように社会文化適応と言語発達という問題を考える事例として、日本の社会において彼らの言語環境は非常に重要なサンプルを提供している。特に言語集団という視点からの研究は今後の日本における様々な言語集団の可能性を考えると特に必要性が高いものと言える。本研究ではこれまで明らかになったことをふまえて、彼らを一つの言語集団としてとらえ、日本人集団とのグループダイナミズムが彼らの中国語と日本語という二言語発達にどのように影響を及ぼすのかを、特に彼らのアイデンティティー形成という観点から明らかにすることを目的とする。
先行研究
日本の社会における中国帰国者の子弟の適応と言語発達を考えるには、前述したように言語習得の分野にとどまらず、異文化コミュニケーションといった社会学的分野、自己概念の形成といった教育心理学的分野なども視野に入れなくてはならない。しかしこれらの分野の成果をいたずらに取り入れて、調査・研究を行ってもそれぞれの成果の範疇を越えるものにはならない。またアメリカやヨーロッパにおける移民のバイリンガリズム研究がはたしてそのまま日本の事例に応用できるのかも不明である。本研究は日本社会における日本語を母語としない言語集団のバイリンガル能力をテーマとしているが、それに適した研究の理論的な枠組みを考えなくてはならない。そのためにはこれまでの先行研究を本研究に即した統合的な視点で見直す必要がある。本研究の実態に即した理論的枠組みを構成するために、ここではまず第二言語習得における社会文化的な影響を扱った代表的な研究を以上の観点から整理し、現時点での成果とその問題点を論じる。
前述したように、ヨーロッパやアメリカ、カナダといった移民、移住者を多く受け入れている国々、あるいは少数言語集団を抱えている国々では第二言語習得の問題を社会文化的な文脈で扱った先行研究は多い。これまでの代表的な先行研究の傾向を見ると、2種類に大別できる。それはLambert
and Gardner(1972), Gardner(1985)、Gardner and McIntyre(1991,
1992), Baker(1992)などの言語に対する態度と動機付けから目標言語の習得を扱った研究と、社会言語学的な立場から言語集団との社会文化的距離という観点で第二言語習得を扱ったSchumann(1976)、Giles
and Byrne(1982), Beebe and Giles(1984)などの研究である。これらの先行研究は第二言語習得研究の分野では以下のように分類されている。前者の態度、動機付けに関する研究は「個人内の要因」(personal
factor: Brown, 1994.)、あるいは「学習者の個人差」(individual
learner differences: Ellis, 1994)、として分類され、また後者は「社会文化的要因」(sociocultural
factors: Brown, 1994. social factors: Ellis, 1994)として分類されている。このうちGardnerのSocio-Educational
ModelはEllis(1994)の文献研究では両方にまたがって論じられている。
文献研究の視点では以上のような分類法になることは仕方がないのかもしれないが、異文化を持った言語集団の適応と第二言語習得の仕組みを考えた場合、両者は不可分の関係にあることがわかる。つまり、移住という社会文化的環境の外的変化が存在し、それがその個人のアイデンティティーと言語発達に影響を与えるという過程となる。その意味でこの二つの要因は一連の流れとしてとらえる必要がある。
まず社会文化的要因の代表的なモデルとしてはShumann(1978)の文化変容モデルがある。このモデルは、「学習者が目標言語集団にどれだけ適応できるかが第二言語習得を左右する」ことを基本的な考え方としている。また、第二言語習得の成功に影響を与える社会文化的要因として以下のようなものをあげている。
- 目標言語集団と出身言語集団との社会的立場の格差
- 目標言語集団と出身言語集団との同化への指向性
- 社会的機関の共有
- 出身言語集団の規模
- 目標言語集団と出身言語集団との文化の類似性
- 目標言語集団と出身言語集団の相互の肯定的な態度
- 目標言語社会での滞在期間
Shumann(1978)によって初めてこれらの社会文化的な要因は整理された形で提示された。その意味で検討すべき要因であると言えるが、その要因の決定方法に大きな問題が残る。Shumann(1978)はこれらの要因を固定的に決定しており、ステレオタイプ的な見方になる可能性がある。この研究でShumann(1978)は上記の要因をラテンアメリカ社会出身のアメリカ合衆国への移住者の例を下に決定しており、その根拠は示されていない。さらに第二言語習得の過程の説明がなく、その意味でブラックボックス的な研究であると言える。
次にGiles and Byrne (1982) のThe Inter-group Modelを例に取り考察する。このGiles
and Byrne(1982)のモデルはShumann(1978)の文化変容モデルの社会文化的要因と心理的要因を統合・発展させた形で、グループ間のダイナミズムを柱とした「適応理論」(accomodation
theory)を提示している。彼らのモデルを要約すれば次のようになる。
- 自己集団に強いアイデンティティーを持つかどうか
- 自己集団を目標言語集団に対して肯定的に、あるいは否定的に比較するかどうか(あるいは全く比較しないか)
- 自分の属する集団の民族的、言語的活力を高いと受けとめるかどうか
以上の要因がその言語集団に対して収束
(convergence)、あるいは分岐(divergence)をおこし、第二言語習得に対して影響を持つとしている。つまり学習者が目標言語集団に対してどのように自己評価をするのかが、収束と分岐を決定する要因となる。
彼らの理論で注意すべき点は、目標言語を習得しようとする高い動機付けにつながるものとして、目標言語社会に対して強い動機付けを持つことと、自己の言語集団を否定的にはとらえない態度をあげていることである。つまり出身の言語集団を肯定的にとらえつつ、目標言語社会へ収束(
upward convergence)することが、目標言語の高い動機付けと高い習熟度につながるとしている。
しかし、適応理論に対しては、「既存の知識を言い換えたもの」にすぎないとする批判(Edward,1985)もある。確かに上記の決定要因が実証的に検討されていない以上、他のモデルと同じように「ブラックボックス」的となっていることは否定できない。ただ、個人内の目標言語の習熟度を目標言語集団への自己認識と関連づけた点で、この理論の様々な言語集団への応用を可能にしている。
次に個人内の要因の先行研究として、Gardner
(1985)の社会-教育学的モデルをあげる。このモデルは文献研究の中では社会文化的要因と個人内要因にまたがって扱われることが多いがその理由はこのモデルが提示する4つの段階のうち第一段階を社会文化的背景から始まっていることによる。しかし、全体として主に第2段階から第4段階、つまり個人差の段階というプロセスに力点が置かれているので、ここでは個人内要因のモデルとして検討する。
図 1
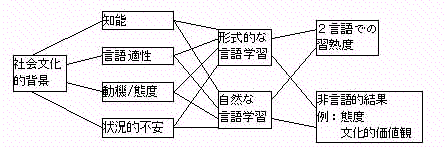
Gardner (1985)のモデルはそれまでの先行研究をつなぎ合わせて作り上げているのではなく、それぞれの段階において実証的に検討されている
(Gardner, 1985, p152)。その意味でこのモデルの信頼度は高い。しかし、それぞれの段階での広がりがあまりにも幅が広く、それを全体として統合させることが可能なのか疑問が残る。特に、第一段階での社会文化的背景の影響についてはきっかけとなるだけでなく、その後の習得過程においても継続的に影響を持つと考えられ、その意味でさらに詳しく検討する必要性がある。
Gardnerは個人内の要因としてさらに態度と動機付けについて研究を行っている。その一例としてGardner
and McIntyre (1992)の目標言語への態度と動機付けの研究を取り上げる。この研究では言語学習に対する動機付けがテーマとなっている。動機を統合的動機、道具的動機の2種類に分類し、特にこの研究では統合的動機と言語学習の相関をテーマにし、統合的動機を「その言語グループとの相互交流のために、言語や文化を理解したいという欲求」と位置づけている。この研究はカナダにおけるフランス語学習(コンピュータを使った語彙学習)というコンテクストで、教室内の実験室的な状況でおこなわれ、統合的動機の要素を考える上で考慮すべき項目をあげている。以下はその要素である。
- 動機の程度
- フランス語学習への欲求度
- フランス語学習への態度
- 統合的意識
- フランス語系カナダ人への態度
- 外国語文化への興味
以上の項目で、それぞれ具体的な項目別にリカート法で質問を行っている。結果として語彙の学習において学習環境への態度と動機に強い関連があるとしている。この研究では動機付けと態度を複数の要素からなる複合的なものとしてとらえいるが、必ずしもその区分は明確とは言えない。この統合的動機と道具的な動機の第二言語習得への影響に関しては様々な論議がなされ、確定したものとは言えない。しかし少数派民族集団の多数派集団への言語的態度という文脈で考えた場合、有益な考え方と言える(Baker,
1992, p 34)。
また以上の2大要因の研究とは別に、言語発達と知能、あるいは学力といった教育的な視点でのバイリンガル研究の成果がある。第二言語習得における社会文化的影響のモデルにしろ、個人内の要因のモデルにしろ、必ずしもそのプロセスにおける個々の要因について実証的とは言えず、ブラックボックス的なものになってしまう傾向がある(Baker,
1992, p29)。その個々の要因を学校現場などに見られる具体的な変数としてミクロ的に観察し、解明しようとするのが教育的な視点からのモデルである。
Baker(1993)はこれまでのバイリンガル教育のモデルを参考に4分割の組織的なモデルを提唱している。それは全体的な枠組みとして次の4つの変数をあげている。教師と生徒の様々な特徴としてインプットの変数、言語発達の成果や長期的な影響としてのアウトプットの変数、学校や地域などの性質としてのコンテクストの変数、最後に生徒と教師、あるいは生徒同士の相互作用としてのプロセスの変数である。それぞれの変数は以下のようなサブカテゴリーを持つ。
(1) インプットの変数
(A) 教師の特徴
・ 言語の熟達度
・ 言語的な知識
・ 文化的な知識
・ 教師の能力と態度
(B) 生徒の特徴
・ 言語の熟達度
・ 言語に対する適性、態度、動機
・ 言語、文化的な背景
(2) アウトプットの変数
・ 各言語の到達度
・ 各言語に対する態度
・ 社会文化的な統合
・ 自尊心
・
長期的な影響(例:雇用、文化的な関わり、家族の言語)
・ カリキュラムを通しての到達度
(3) コンテクストの変数
・ 言語の目標に関する社会の性質
・ 言語と文化に関する地域社会の性質と目標
・ 学校の性質と目標
・ 教室の性質と目標
(例:生徒間の言語のバランス)
・ カリキュラムの性質
(4) プロセスの変数
・ 生徒と教師の相互作用
(例:2言語の使用割合)
・ 生徒同士の相互作用
・ 各教科の教材の使用
(教師と生徒の教材の扱いに関する理解度)
以上の変数はバイリンガル教育の現場に関わる要素を効率的にまとめている。上記の要素のうち、特にプロセスの変数は注目すべき変数である。インプットの変数やアウトプットの変数などは教師や生徒の性質といったどちらかといえば固定的な変数が要素として扱われているが、言語習得がコミュニケーションを本来の目的としているという意味で、「相互作用」という動的な要素はそれらにもまして重要な要素である。また個々の生徒だけではなく、「言語集団」としての生徒を考えた場合、言語集団同士のダイナミズムが生まれる(Giles
and Byrne, 1982) 。
以上の先行研究を第二言語能力の発達のプロセスモデルとして統合的にとらえ、以下のように整理した。まず、第二言語習得の大きな流れを社会文化的要因のモデルと個人内の要因のモデルで設定し、その流れに影響を与える個々の要因としてバイリンガル教育のモデルの変数をとらえるというものである。そして、この変数のそれぞれを実証的に検討し、また大きな流れの中にフィードバックすることで全体のプロセスを理解できると思われる。
本研究の仮説
これまで述べてきたように、バイリンガル能力とその社会文化的適応の問題を考えるには個別の研究分野にとどまっているのでは不十分である。社会言語学的アプローチと教育心理学的アプローチの両者の視点が必要となる。特にこれまでの言語習得のモデルでは特定されなかった社会文化的要因、特に多数派言語と自グループとのグループダイナミズムが個人内の態度や動機付けにどのように影響を与え、実際の言語発達として出現するのかを明らかにするためには、後者の視点は重要となる。
先行研究を検討しても分かるように、第二言語習得のモデルを設定するのは困難な作業である。たとえば目標言語に対する肯定的な態度や高い動機付けが必ずしもその言語をうまく習得することに結びつくとはかぎらない。言語習得への動機を考える上で、中国残留孤児の精神医学的な研究に興味深い事例がある。中国帰国者の適応初期の精神的課題の不適応ないし、抑鬱反応の誘因として最も大きなものが日本語学習困難であった(江畑他,
1996)。これはその配偶者の精神的課題のうち日本語学習困難が4番目であることを考慮すると、日本社会に早くとけ込みたいという動機の高さがかえって精神的負担となっていることを示している。このように言語に対する態度と動機付けの問題は複雑なシステムであり、説得力のある理論的な枠組みが必要となる。
異文化、異言語を身につけた児童の言語の能力と日本におけるの適応と言語発達を考えるには、その児童の特殊性を考慮する前に、一般的に学校と家庭という環境の中で子供たちがどのようにその学習を達成するのかを考えなくてはならない。子供たちの学習発達を彼らを取り巻くものたちと彼らの心理的要素という関係でとらえる時、以下のモデル(蘭,1989)が役に立つ。
図2
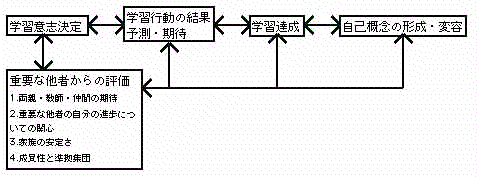
子供の自己概念の発達と重要な他者からの評価と能力の自己評価の関係について
(Brookover & Erickson,1969,1975から作図)
蘭(1989)はこれまでの自己概念の発達に関わる研究の成果をふまえてこのモデルをまとめているが、子供の自己概念の形成・変容過程が重要な他者からの評価を媒介とする能力の自己評価によって大きく影響するとしている。その影響の筋道は以下の通りである。
1.
重要な他者からの評価によって自己評価が修正され、自己概念が変化する段階
2.
それによって学習課題に対する意志決定がなされ、学習行動が成立する段階
3.
学習課題が達成されることによって自己の役割や能力についての自己概念、自己に対する道具的価値や内発的価値を自覚する段階
4.
その結果として、自己概念がさらに形成・変容する段階
蘭(1989)は、以上の過程を通して自己を価値的に評価する自尊感情が高められ、そして、この自尊感情がさらに高い学業達成を促すと考えられるとしている。蘭(1989)は上記のモデルの中でまず、子供の自己概念を形成する要素として「重要な他者からの評価」をあげ、さらにこの評価が学習行動に結びつくとしている。
子供の自己概念を理解するために蘭(1989)は以下のような枠組みも提示している。
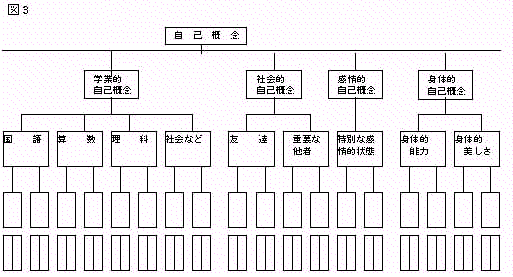
蘭(1989)は一般的自己概念を頂点として、階層的にそれを形成する要素を示している。つまり自己概念の下には学業的、非学業的(社会的、感情的など)自己概念があり、さらにその下位領域として個別の要素(学業的:国語など、非学業的:重要な他者など)がある。そして、そのサブカテゴリーがあり、そのサブカテゴリーは各々の場における行動の評価へと細分化される。
以上はいわゆる一般の子供たちの自己概念のモデルであるが、帰国子女や中国残留孤児の子弟などの自己概念の形成期に大きな言語環境の変化を経験するものの場合は一体どうなるのだろうか。学業的自己概念の場合、第一言語の発達が第二言語への転移がその知的発達を左右するという研究がある。つまり第一言語の発達が第二言語へとうまく転移した場合、個別の学業の成績は伸びる可能性があるというものである(Cummins,
1984b, 1986)。その理論にしたがえば、それにともなって学業的自己概念も発展的に形成される。
非学業的自己概念の場合、友達や重要な他者とのコミュニケーションがその評価に大きく影響する。大きな言語環境の変化を経験しない一般の児童の学力形成の場合は、その学業発達の要因を日本語という同一の言語発達の中で考慮することができる。つまり言語環境が他の児童と均一であると考えられるが、帰国生などの場合は学校という集団の中の少数言語グループとしてとらえる必要がある。そこには言語グループ同士の力学が働く。自分の属する言語集団に対する他者の評価が、自己概念の形成に影響を及ぼすことが考えられる。蘭(1989)のモデルに補足すれば以下のようなモデルが考えられる。自己概念のサブカテゴリーとして社会的自己概念があるが、この社会的自己概念はその準拠集団としての言語グループという枠組みの中で、他者からの評価を受け、本人たちもその評価によって、自己評価を修正し、自己概念を形成するのである。さらにこれによって、学校の中の学習課題に対する意志決定がなされ、学習行動が成立する(蘭、1989)。ここで言う学習行動とは学校における認知的活動全体を指す。日本語を第二言語として習得しようとするものには、日本語の獲得行動も学習行動の一つと考えられる。
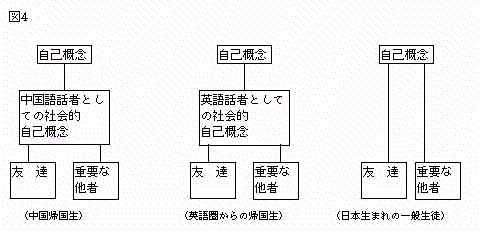
自分の属する言語グループに対する評価の受けとめ方によって、学習行動が影響を受けることは、第二言語習得の先行研究からも予想できる。Giles
& Byrne(1982)によれば、少数言語集団の目標言語集団に対する受けとめ方が目標言語の習得に影響するとしている。箕浦(1991)はアメリカにおける子供の異文化体験を研究し、その英語力形成に最も関与しているものとして、アメリカ人との交友密度をあげ、次のように述べている。
英語習得の社会的文脈であるアメリカ人との交友密度自体が、英語圏に入った年齢や居住期間との相関が高いため、「何歳で来米し、もう何年アメリカにいるか」を聞けばかなり正確に子供の英語力を推定しうることを調査結果は示していた。
箕浦(1991)の示している英語力の形成要因は、居住期間に比例したアメリカ人との交友関係を通じた英語のinputの総体量であるが、inputを促進、あるいは停滞させる要因については触れてはいない。促進あるいは停滞要因として自分の属する言語集団への評価があり、この評価が第二言語である日本語の習得への態度と動機付けに影響を及ぼしていると考えられる。
また高校生レベルの中国引揚者の子弟(中国帰国生)の言語発達の調査(清田、1995)では、彼らの日本生まれの生徒に対する不満感と日本語発達に対して相関が見られた。また第一言語である中国語に対して高い象徴性が見られた。さらに全体として日本語が道具的な動機で学ばれているのに対し、中国語は統合的動機で学ばれている傾向があるなど両言語の発達がアイデンティティーの形成に関わることも明らかになった。これは日本人という言語グループに対する自分の中国話者としての意識のあらわれともみられる。
この予想をもとに次のような仮説を設定した。それは帰国子女が自己概念を形成する際に、日本語以外の言語話者として自分を意識し、自分の属する言語グループを少数言語グループとして、学校内の一般の生徒の使用する日本語を多数派言語としてとらえ、そのグループ間の力関係が個人の二言語発達に対して影響を及ぼすというものである。これは学校内という限られた空間に二つの言語が存在することであり、ダイグロッシア(Ferguson,1959.
Fishman,1972)の枠組みを当てはめることができる。それは学校内の言語集団の多数派としての日本語と少数派としての中国語という力関係から見れば高位の言語変種(日本語)と低位の言語変種(中国語)であり、「両者の関係は中立的ではなく差別的となる」とされている。
Baker(1994)のまとめた表から中国帰国生にとっての二言語として高位の言語を日本語、低位の言語を中国語と見れば、この状況はそのままあてはまる。
| 使用状況 |
多数派言語(日本語) |
少数派言語(中国語) |
| 1.家庭・家族 |
|
● |
| 2.学校教育 |
● |
|
| 3.マスメディア |
● |
|
| 4.仕事・商業活動 |
● |
|
| 5.共同体内社会文化活動 |
|
● |
| 6.親戚、友人とのやりとり |
● |
|
| 7.行政府とのやりとり |
● |
|
このダイグロッシア的な力関係は学校という環境の中で可変的に帰国生の二言語の習得に影響を与えると予想される。さらに両言語の力関係が対立的に推移する中で、二言語の習熟度の変化により、中国帰国生の言語話者としての自己概念の形成に影響を与えていると考えた。
研究の方法
以上の仮説を実証的に検討するために、Baker(1994)のバイリンガル教育の4分割の変数の枠組みを利用した。さらに前回の調査をふまえて中国帰国生にとって重要と思われる要素を以下のように設定した。
(1) インプットの変数
- 帰国生の中国語、日本語の熟達度
- 帰国生の日本社会、中国社会への態度
- 自信
- 現在の学習および将来への意欲
- 交友関係(準拠集団)
- セルフ・エスティーム(自尊心)
- 教師の期待
- 中国話者としての自己意識
(2) アウトプットの変数
- 帰国生の中国語、日本語の到達度
- 帰国生の日本社会、中国社会への態度の変化
- 自信の変化
- 現在の学習および将来への意欲の変化
- セルフエスティーム(自尊心)の変化
- 交友関係(準拠集団)の変化
- 教師の期待の受けとめ方の変化
- 中国話者としての自己意識の変化
(3) コンテクストの変数
- 学校の性質と目標
- 教室の性質と目標
- カリキュラムの性質
- 地域社会の性質
(4) プロセスの変数
- 教師との相互作用
- 一般の日本人生徒との相互作用
- 中国語、日本語の使用の割合
以上の変数を東京都立高等学校の受け入れ校の第一学年に対する中国帰国生への語彙力テストと質問紙調査、また担当教員への質問紙調査によって調査する(巻末の付録を参照)。東京都立高等学校の受け入れ校の中国帰国生を被験者とした理由は各学校の受け入れ環境がほぼ同じことと、年齢に大きな差がないことである。
これらの調査を1年毎に3回行い、入学時から3学年までのインプットの変数からアウトプットの変数の変化を調査する。長期的に追跡調査を行うことにより、これまで解明されなかった各要因が実証的に検討できると思われる。各変数のデータは多変量解析の統計処理を行う。さらにそれぞれの学習と日本語習得の進度に関して担当の教師への質問紙調査も行う。あわせて大学に在籍する中国帰国生に質問調査を行い、上記のデータを検討する際の質的な補足をめざす。
調査結果(1997年 10月 1日現在)
現時点では4分割の変数のうち、(1)
インプットの変数の変数の調査が終了している。これらの変数は1年後に追跡調査を行い、その推移、つまりアウトプットを調べることになる。まず(1)
インプットの変数の結果を報告する。
年齢
| 年齢 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 人数 |
2
( 5%) |
16
(41%) |
10
(25%) |
8
(20%) |
3
( 7%) |
15歳から19歳まで、計39人である。年齢は15から17までが28人(71%)を占めているが、やや学齢より上の傾向がある。
出身地
| 出身地 |
黒竜江省 |
遼寧省 |
吉林省 |
福建省 |
湖南省 |
河北省 |
江蘇省 |
四川省 |
| 人数 |
26 |
2 |
2 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
在日期間
| 滞在年数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 人数 |
8(20%) |
7(17%) |
6(15%) |
5(12%) |
7(17%) |
3( 7%) |
3( 7%) |
旧満州にあたる黒竜江省が26人と全体の約60%を占めている。また在日期間が1年から3年以内のものが21人(53
%)
と過半数を占めており、全体的に在日期間は浅い。
語彙力テスト 語彙力試験は20問の設問で、1問につき1点、それぞれの語彙の正しい意味を選択する形式である。その結果は以下の通りである。中国語の平均点15.05、標準偏差4.27である。日本語の平均点12.33、標準偏差4.63であった。
中国社会、日本社会にたいする好感度
「あなたは中国(日本)の社会や文化が好きですか」という質問に、「とても好き」から「とても嫌い」の5段階の尺度で答えさせた。併せてそれぞれの国民の好感度をどう思うかという質問も行った。「とても好き」を5ポイント、「とても嫌い」を1ポイントとして点数化した。この項目はいわゆるそれぞれの言語社会に対する態度を調べるものである。
ここで興味深い結果は、中国社会への好感度が平均3.92(標準偏差0.69)である対し、日本社会に対しては平均3.38と、日本社会よりも中国社会への好感度が高いことである。この理由は在日期間が比較的短いことから出身国である中国社会により好感を持つことにあるかも知れない。
自信
行動における自信は、自分をとりまく環境における適応の度合いを示す重要な変数のひとつと考えられる。この項目では「人から悩みを相談されたら自信を持って答えられる」と「自分の心を素直に人に言える」の二つの項目で質問を行った。答え方は「強く思う」から「まったく思わない」まで、5段階のリカート法で質問し、5から1ポイントまで点数化した。前者の平均値は3.15(標準偏差0.92)で、後者は3.62(標準偏差0.97)であった。
意欲
ここでは現在の学習と将来に対する意欲を質問した。「学校で熱心に勉強に取り組んでいる」と「将来自分の能力を最大限に伸ばせるよう、色々なことをやってみたい」の質問に対し、前者は平均値3.33(標準偏差
0.91)で、後者は4.15(標準偏差0.57)と現在の学習意欲より、将来の意欲の度合いが高くなっている。
セルフ・エスティーム
日本生まれの級友からの自分に対する評価をどのように判断しているか、また自分は日本生まれの級友をどのように評価しているかを尋ねた。これは前者は3.38(標準偏差0.80)に対し、後者は3.17(標準偏差0.81)と、自分の日本人の友人に対する評価の方が低くなっている。
交友関係
「日本生まれの級友は自分と仲良くしたがっている」と「自分は日本生まれの級友と仲良くしたい」の二種類の質問に前者は3.38(標準偏差0.80)と後者は4.10(標準偏差0.63)と、自分と日本生まれの級友との間に落差を感じていることを示している。また休み時間を過ごす相手として「いつも中国帰国生」(5ポイント)から「いつも日本生まれの級友」(1ポイント)まで設定し、平均値は3.74で半数以上が「いつも中国帰国生」または「どちらかと言えば中国帰国生」と答えており、帰国生同士で固まる傾向を示している。
教師の期待
教師の「自分の成績」と「将来」に対する期待をどのように受けとめているかを質問した。「成績」が3.97(標準偏差0.76)に対し、「将来」は3.69(標準偏差0.75)であり、「成績」の方が高い値を示している。これは帰国生自身の意欲とは逆の結果となっており(学習3.33、将来4.15)、自分自身の意欲の低い分だけ、教師の期待を意識しているのかもしれない。
将来の子供の言語
将来自分の子供が中国語を話すことを望むかという質問には、平均4.07(標準偏差0.79)と高い数値になっている。言語の継承性を重要に感じていることが示されている。この変数に関しては前回の調査(清田,
1995)でも高い象徴性が認められた。母語としての中国語の持つ意味に関してさらに考察が必要と思われる。
言語使用
話し相手によって言語を使い分けている傾向が示されており、特に親との場合は「いつも中国語」であるのに対し、兄弟の場合は「どちらと言えば日本語」、「いつも日本語」という結果になっており、世代による言語移行が進んでいる。また自分の使用言語も日本社会と接する機会を中心に日本語が増え、ここでも言語移行の傾向を示している。
相関
それぞれの変数同士の相関関係を多変量解析の単相関分析で求めた。変数同士の相関がそのまま因果関係に結びつくわけではないが、原因と結果を考察する手がかりとなり、それぞれの変数の特徴を理解するのには有効である。以下は相関が認められたものである。(*:5%,
**:1%)
| 在日期間 |
**中国語語彙テスト、**日本語語彙テスト |
| 将来の意欲 |
*中国社会に対する自分の好感度、*中国社会に対する日本人の好感度(自分が判断する)、**自信(感情表現)、*学習意欲 |
| 休み時間の相手 |
**在日期間 |
| 日本生まれの級友の自分に対する評価 |
**日本人の中国社会への好感度、*自信(感情表現)、*学習意欲、**将来の意欲 |
| 日本生まれの級友の自分に対する親密度 |
*在日期間、**日本生まれの級友の自分に対する評価 |
| 日本生まれの級友に対する自分の評価 |
**日本社会の対する自分の好感度、**日本社会に対する中国人の好感度(自分が判断する) |
| 日本生まれの級友に対する自分の親密度 |
*中国社会に対する日本人の好感度(自分が判断する)、*日本生まれの級友の自分に対する親密度 |
| 教師の自分の学習への期待 |
*日本語語彙テスト、*将来の意欲、*休み時間の相手、*日本生まれの級友の自分に対する親密度 |
| 教師の自分の将来への期待 |
*日本社会に対する自分の好感度、*休み時間の相手、*日本生まれの級友に対する自分の親密度、**教師の自分の学習への期待 |
| 将来の子供への中国語継承 |
*学習意欲、**将来意欲、*日本生まれの級友に対する自分の親密度、*教師の自分の学習への期待、*教師の自分の将来への期待 |
上記の相関があると認められるもののうち、中国帰国生の教育環境における社会文化適応に関して重要と思われるものを考察し分析する。
- 在日期間
- 在日期間に関しては中国語の語彙テストがマイナスの1%**の有意水準であり、日本語の語彙テストがプラスの1%**の有意水準であった。これは日本における滞在期間が長いほど日本語の習得が進み、逆に中国語の喪失が進んでいることを示している。言語においてもはっきりと同化傾向が現れている。このことは後述する将来の子供への中国語の継承と比較すると興味深い相関と言える。
- 将来の意欲
- 将来の意欲に関しては、中国社会に対する帰国生自身の好感度、中国社会に対する日本人の好感度(帰国生が判断する)が5%*の有意水準で、自信(感情表現)が1%**、学習意欲が5%*の有意水準であった。将来の意欲と中国社会への肯定度の相関は、「自分の出身集団を目標言語集団に対して否定的に比較しない」というGiles
and Byrne(1982)があげている第二言語習得が進む要因と関連できる。これは帰国生のアイデンティティーの安定と結びつくことも考えられる。
- 休み時間を過ごす相手(準拠集団)
- 授業時間と違い、休み時間は自発的な交友関係が反映する。その交友関係を学校における準拠集団ととらえた。「いつも中国帰国生」(5ポイント)から「いつも日本生まれの級友」(1ポイント)までで、在日期間とマイナスの1%**の有意水準となっていることは滞在期間が長くなるほど日本生まれの友達との交友関係が増えることを示している。2言語との関連で考えれば、友人関係の広がりがそのままそれぞれの言語習得に結びついている傾向がある。
- 日本生まれの級友の自分に対する評価(帰国生自身が判断する)
- この項目は自分が日本生まれの級友にどのように評価されているのかを問う質問で、本研究の仮説の「他者の自己概念に及ぼす影響」と関連が深い。相関が認められたのは中国社会に対する日本人(帰国生が判断する)の好感度*、自信(感情表現)**、学習意欲*、将来の意欲**であった。学校内の重要な他者(蘭,1989)の評価が自信や意欲など自己概念の肯定的な形成と結びついていることは仮説の予想に沿った結果となっている。
日本生まれの級友の自分に対する親密度(帰国生自身が判断する)
在日期間*、日本生まれの級友の自分に対する評価(帰国生自身が判断する)**に相関が認められる。これも滞在期間が長くなり、日本生まれの友達と交友関係が進むにつれて、それがそのまま友達の自分の評価へと結びついている。
- 日本生まれの級友に対する評価
- 日本社会に対する帰国生自身と帰国生が判断する中国人の好感度が両方ともに1%**の有意水準であった。これは自分の日本生まれの級友に対する親密度が日本人の中国社会への好感度(帰国生自身が判断する)と日本生まれの級友の自分に対する親密度(帰国生自身が判断する)に相関が認められる(両者とも5%*)ことを合わせて考えると日本生まれの友人と日本社会との関連が認められ、帰国生にとって日本生まれの友人が日本社会を代表した存在と映っているとも考えられる。
- 教師の学習への期待
- 日本語の語彙テストと休み時間の相手が5%*のマイナスの相関があり、将来の意欲と日本生まれの級友の自分に対する親密度(帰国生自身が判断する)が5%*のプラスの相関となっている。考えられる分析としては、被験者が全体的に在日期間が浅く、まだ日本語習得が十分でない分だけ、教師の期待を感じているということである。
- 教師の将来への期待
- 日本社会への自分の好感度*、休み時間の相手*、日本生まれの級友に対する親密度*、教師の学習への期待**に相関が認められた。休み時間の相手に関しては学習への期待同様にマイナスの相関が認められた。つまり学校における交友相手が帰国生同士のうちは教師から感じる期待度が低いということになる。
- 将来の子供の言語
- この変数に関しては特に興味深い結果が得られた。この変数と相関が認められたのは、学習意欲*、将来の意欲**、日本生まれの級友に対する親密度*、教師の学習への期待**、教師の将来への期待**である。これらの変数が特に中国帰国生の肯定的な自己概念の形成にとって重要な要素であることに注目したい。帰国生の第一言語である中国語を将来自分の子供に継承したいという希望が排他的な中国人としてアイデンティティーの確立につながるのではなく、むしろその象徴性を支えとして自己を肯定的にとらえることにつながっているとみられる。
彼らの母語としての中国語は単にコミュニケーションの道具としての言語という存在を越えた意味を持っていることが予想される。たとえば言語集団の象徴性や歴史性に対してどのような意味を持つのか、さらに深い検討が必要である。
まとめと今後の展望
本研究の大きな枠組みとして次のようにまとめられる。
(1)これまでの第二言語習得における社会文化的な影響、また個人内の影響の先行研究を統合的にとらえる。
(2)中国帰国生の教育環境的な視点から影響を持つとみられる変数をインプットとアウトプットとして分け、長期的に追跡調査を行う。
(3)中国帰国生を言語集団としてとらえ、特にかれらの社会文化的な適応と言語発達において、言語話者としての自己概念の形成という視点が重要な要素となることをその仮説とする。
まず(1)に関しては、新たな統合型のモデルを作るには、これまでの先行研究をさらに体系化する必要がある。この準備論文では第二言語習得における社会文化的な影響、また個人内の影響の先行研究の大きな流れをつかむために、特に代表的なもののみを取り上げた。しかし、言語グループのコミュニケーション理論として重要な理論である「適応理論」(Speech
Accomodation Theory)に関してもまだ多くの重要な研究がなされている(
Beebe and Giles, 1984., Ball, Giles, Byrne and Berechree,1984.,
Giles and Johnson, 1987. Giles, Coupland and Coupland, 1991)
。またGardnerの社会 -
教育モデルにしてもそれを基にしたモデルのヴァリエーションについてもさらに検討を加える必要がある。
現時点では日本における中国引揚者の子弟の言語発達の研究についてはほとんど前例がなく、カナダやアメリカの先行研究を参照する他はない。しかし、これまでの先行研究の対象は、例えばウェールズの少数言語と多数言語というコンテクストやカナダのフランス語のイマージョン教育、またアメリカ合衆国の移民のバイリンガル教育の研究といった分野に限られてきた。これらの先行研究を中国引揚者の子弟の言語発達の研究に応用するにはさらに緻密な検討が必要となろう。
(2)に関しては、現時点では東京都立学校の受け入れ校の1年生に在籍する中国帰国生のインプットの変数を調査している。今後はこのインプットの変数がアウトプットの変数としてどのように変化するかを追跡調査する。現時点での調査では中国語と日本語の両言語に特に相関が見られたのは在日期間であった。この後、それぞれの学校環境の中での人的な交流を経て様々な影響があらわれることが期待される。
また個々に報告した調査以外に受け入れ校のコンテクストの変数を調べるために、それぞれの生徒の担当の教師の質問調査を行っている。さらに大学レベルの帰国生に質問調査を行い、高校レベルの変数と比較、検討を行う予定である。
(3)に関しては自己概念と学習の発達の理論に関して、さらに緻密な理論構築が必要である。特に(2)で得られたデータの分析に際して、認知心理学的な立場からの知見が役に立つと思われる。例えば、Vygotsky
(1970)は学習のコンテクストとして他者が重要な役割を持つことを指摘している。実際にこの理論をアメリカにおける移民の言語発達に応用している研究もある(Cummins,
1994)。また、Lave and Wenger (1991)は「正統的周辺参加」(legitimate
peripheral participation)という概念を提唱している。これは学習者が実践を行う共同体の正式のメンバーとして活動に参加しながら、その活動を理解していくなかで、学習者の自己認識が変化していくというものである。この理論は多数言語社会における少数言語話者の第二言語習得という状況に置き換えると、興味深い知見を提供している。これらの先行研究を有機的に結びつけながら、本研究の理論構築を計っていきたい。
参考文献
Baker,C.,1992, Attitudes and Language. Clevedon:
Multilingual Matters.
Bake, C., 1993, Foundations of Bilingual Education.
Clevedon: Multilingual Matters.
Brown, H.D. 1993, Principle of Language Learning and Teaching
Third Edition. New Jersey: Englewood Cliffs.
Cummins, J. and Swain, M. 1986, Bilingualism in Education.
New York: Longman.
Harley, B., Allen, P., Cummins, J. and Swain, 1990, The
Development of Second Language Proficiency. Cambridge:
Cambridge University Press.
Edwards,J.,1985,Language, Society and Identity, Oxford:
Blacwell.
Edwards,J., 1994, Multilingualism, London:Pnguin Books.
遠藤満雄、1992、『中国残留孤児の軌跡』、三一書房。
Ellis,R., 1994, The Study of Second Language Acqusition,
Oxford:Oxford
University.
江畑敬介・曽文星・箕口雅博、1996、『移住と適応ー中国帰国者の適応過程と援助体制に関する研究』、日本評論社。
Fishman, J. Language & Ethnicity in Minority
Sociolinguistic Perspective.
Clevedon: Multilingual Matters.
Gardner,R.C., 1985, Social Psychology and Second Language
Learning, London:
Edward Arnold.
Giles,H. and Byrne, J.L., 1982, An "Intergroup
Approach to Second Language Acquisition", Journal of
Multilingual and Multicultual Development, Vol.3 No.1,
pp.17-40.
長谷川辰雄他、1989、『セルフ・エスティームの心理学』、ナカニシヤ出版。
梶田叡一、1988、『自己意識の心理学』、東京大学出版会。
清田洋一、1995、「バイリンガル能力の発達ー中国残留孤児の子弟を事例として」1995年度東京大学大学院総合文化研究 科言語情報科学専攻修士論文、未公刊。
清田洋一、1997、「日本の文化をどのように扱うか
- 異文化と日本文化の共生」『教職研修 -
総合的な学習の進め方の実践No.3、国際理解教育の考え方・進め方』、教育開発研究所。
Lave, J and Wenger, E., 1991 Situated learning: Legitimate
peripheral participation. Cambridge: Cambridge University
Press
Larsen-Freeman, D. and Long, M.H., 1991, An Introduction to
Second Languag Acquisition Reserch. New York: Longman.
箕浦康子、1991、『子供の異文化体験』、思索社。
文部省教育助成局海外子女教育課、1995、『海外子女教育の現状』中西晃、1989、『中・高校生の国際感覚に関する研究報告書ー青少年時代の異文化体験が人格形成に及ぼす影響』東京学芸大学海外子女教育センター。
日本国際教育協会、1995、『日本語能力試験一級、二級』凡人社。
小川津根子、1995、『祖国よ「中国残留婦人」の半世紀』、岩波書店。
小野博、1994、『バイリンガルの科学』 講談社。
Schumman,J., 1978, The Pidgenization Process:A Model for
Second Language Acquisition, Rowley, MA:Newbury House
総務庁行政監察局編、1997、『教育の国際化をめざして
- 日本語教育が必要な外国人子女や帰国子女の教育の現状と課題』
田中敏、1996、『実践心理データ解析』、新曜社。
田中敏、山際勇一郎、1992、『ユーザーのための教育・心理統計と実験計画法』、教育出版。